みなさん、こんにちは。
テノールから始まり、バリトン、バス、そしてソプラノと順番に声種の違いを説明してきましたが、いよいよ今回で最後です。最後はメゾソプラノとアルトを一緒にしてその声種の違いを説明します!
もくじ
メゾソプラノ、アルトの声種の違い
私たちの声は、その声の高さに応じてだいたいソプラノ、メゾソプラノ、アルト、テノール、バリトン、バスと6種類に分類する事が出来ます。
今回紹介するメゾ・ソプラノ、そしてアルトは女性の中では低めの音域を担うパートとなります。メゾソプラノは、ソプラノよりも少し低い音域を、そしてアルトはさらに低い音域を担当します。
すでにソプラノの声種の違いでも触れましたが、メゾソプラノとアルトの境界線というのは非常に曖昧です。実際にはアルトにはそこまで大きな役が沢山あるわけではないので、仮に正真正銘のアルトの声質を持った歌手でも、メゾソプラノの役柄を多く歌う事がほとんどです。
なので今回はメゾソプラノとアルトを一緒に話していきましょう。
まず、メゾソプラノですが、これは割とはっきりと分ける事が可能です。声質に応じて、コロラトゥーラ・メゾソプラノ、リリック・メゾソプラノ、ドラマチックメゾソプラノと大きく3つに分ける事が可能です。
それからアルトですが、こちらもブッフォアルト、リリック・アルト、ドラマチック・アルト、それと細かく分ける事が可能ですが、その境界線は非常に曖昧な上に、実際にはアルトの声を持った人は非常に少ないので、現場ではメゾソプラノかアルトの人が全部をこなすと言った感じになっています。
まあアルトの方は声質というよりは、どちらかと言えば役柄のキャラクターに応じた分類と考えてもらえば良いです。
オペラというのは非常に簡単にできていて、声が低くなればなるほど年配の役を歌う事が多くなります。もちろん例外もありますが、その規則に照らし合わせると、メゾソプラノやアルトは女性キャラクターの中でも、比較的年配のキャラクターを演じる事が多いです。母親役や、お婆さん役などですね。
またメゾソプラノの大きな特徴としては、なんと女性ではなくて男性(少年)を演じる事が結構多いです。その代表的なものとしてはフンパーディング作曲の「ヘンゼルとグレーテル」のヘンゼルや、モーツァルト「フィガロの結婚」のケルビーノなどが挙げられますね。これらはズボン役とも呼ばれています。
「ソプラノの声種」の回では、この点に触れるのを忘れてしまいましたが、実は数は多くないですが、ソプラノが少年役を演じる事もたまにあります。ヴェルディの「仮面舞踏会」のオスカル役がその代表的なものとなっています。
それでは、それぞれの声種の違いについて順に見ていきましょう!
コロラトゥーラ・メゾ・ソプラノ

それでは早速見ていきましょう!
まず最初に紹介するのが、コロラトゥーラ・メゾソプラノです。コロラトゥーラ・メゾソプラノは、メゾソプラノの中でも最も軽やかな声質を持っています。声質自体は次に紹介するリリック・メゾソプラノとそれほど大きな違いはありませんが、軽やかな特性を生かして、コロラトゥーラのある役柄を歌います。
コロラトゥーラ・メゾソプラノの代表的な役柄としては、「セビリアの理髪師」のロジーナや「チェネレントラ」のアンジェリーナなどが挙げられます。
コロラトゥーラメゾ・ソプラノには、これといってキャラクター的な特徴があるわけではなく、ロッシーニのオペラを歌うのに特化したメゾ・ソプラノという事も可能ですね。
リリック・メゾソプラノの中で、コロラトゥーラを歌う技術がある人をコロラトゥーラ・メゾソプラノと言っても良いぐらい、両者の境界線は曖昧です。実際の所、ほとんどの歌手がどちらも歌ってしまいます。
代表的なコロラトゥーラ・メゾソプラノとしてはチェチーリア・バルトリがあげられますね。ロッシーニの「チェネレントラ」よりアンジェリーナがオペラの最後に歌うアリア、“Non piu mesta”をバルトリの演奏でお聴きください。
- ロッシーニ「セビリアの理髪師」:ロジーナ
- ロッシーニ「アルジェのイタリア女」;イザベラ
- ロッシーニ「チェネレントラ」:アンジェリーナ
- ロッシーニ「タンクレディ」;タンクレディ
リリックメゾソプラノ
リリック・メゾソプラノは、メゾソプラノの中でも比較的軽めの声を持っています。とは言え音域はメゾソプラノという事もあってソプラノと比べると当然低めですし、音色も暗めです。
そのため、リリックメゾソプラノは、女性的なだけではなくて中性的な表現も可能で、少年を演じる事も結構多いです。その代表的なものが「ヘンゼルとグレーテル」のヘンゼルやモーツァルト「フィガロの結婚」に登場するケルビーノですね。声変わりしていない少年の役をやるのにぴったりというわけです。
これらの役柄はスカートではなくズボンをはいていますからズボン役とも呼ばれる事があります。
フンパーディングの「ヘンゼルとグレーテル」から冒頭のシーンを聴いてみましょう。グレーテルを演じるのがグルベローヴァ、ヘンゼルを演じるのがブリギッテ・ファスベンダーとなります。
それからモーツァルト「フィガロの結婚」のケルビーノのアリア“Voi che sapete”も紹介しましょう。このアリアは数あるメゾソプラノの曲の中でも最も有名な曲と言っても良いですね。演奏しているのはアメリカ人のメゾソプラノ、マリア・ユーイングになります。
- フンパーディング「ヘンゼルとグレーテル」:ヘンゼル
- マスネ「ウェルテル」:シャルロッテ
- モーツァルト「バスティアン」:バスティアン
- モーツァルト「コジ・ファン・トゥッテ」:ドラベッラ
- モーツァルト「フィガロの結婚」:ケルビーノ
- モーツァルト「イドメネオ」:イダマンテ
- オッフェンバッハ「ホフマン物語」:ニクラウス
- プッチーニ「蝶々夫人」:スズキ
- ヴェルディ「リゴレット」:マッダレーナ
ドラマチック・メゾソプラノ

ドラマチック・メゾソプラノは、メゾソプラノの中でも最も力強い声質をもったメゾソプラノになります。
ドラマチックメゾソプラノは、カルメンのような特に成熟した女性キャラクターを演じる事もありますが、この声種のキャラクター的な特徴というのはそれほどはっきりしていません。現実的には、ロマン派以降のオペラ全般で大活躍します。
というのもロマン派以降はオーケストラが大きくなった事に伴い、より大きな声量を持った歌手が必要となるためです。そのためヴァーグナーやヴェルディ、またはそれ以降のオペラを歌う歌手にはドラマチックな声質が求められるようになります。
メゾソプラノに限らず、ドラマチックと付く声種は、声がより太く、より力強く、それに伴い声量も大きいです。これによって大きなオーケストラにかき消されずに歌う事ができるというわけです。
音域的には決して低くなるというわけではなく、回数はそれほど多くはないものの、リリックな声種と同じぐらいの高い音も求められます。
またドラマチック・メゾソプラノとドラマチック・ソプラノの境界線はいくらか曖昧で、どちらの役も歌ってしまう歌手も多いです。マリア・カラスはソプラノでありながらカルメンを録音していますし、ヴァルトラウト・マイアーはメゾソプラノでしたが、途中からドラマチック・ソプラノの大役である「トリスタンとイゾルデ」のイゾルデなども歌うようになりました。
それでは数あるメゾソプラノのアリアの中でも私が大好きな、ヴェルディ「ドン・カルロ」よりエボリが歌うアリア“O don fatale”を聴いてみましょう。私は「ドン・カルロ」ではバリトンのロドリーゴ役を歌いましたが、このエボリのアリアの後に大きな場面が控えていましたので、毎回舞台袖から同僚が歌うこのアリアを聴いていました。
まずはロシア人のメゾソプラノ、エレーナ・オブラスツォワの演奏で聴いてみましょう。
ちなみにこちらは、ドラマチック・ソプラノの代表である、ビルギット・ニルソンが同じ曲を歌ったものです。
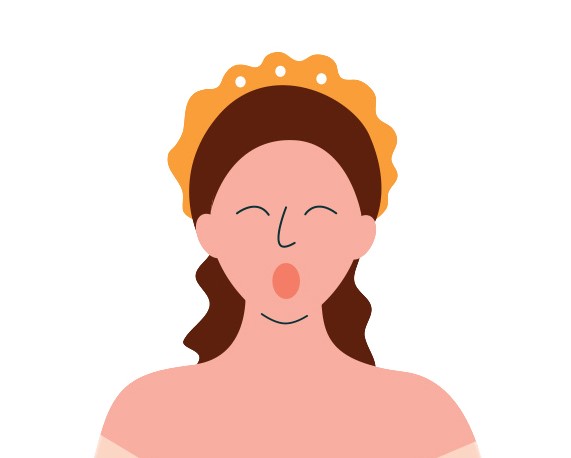
オブラスツォワもニルソンも本当に力強い声ですわね。比べるとやはりメゾソプラノのオブラスツォワの方が中間音がより力強く感じますわ!
- ベッリーニ「ノルマ」:アダルジーザ
- ビゼー「カルメン」:カルメン
- ベルク「ルル」:ゲシュヴィッツ
- チレア「アドリアーナ・ルクブルール」:侯爵夫人
- フンパーディング「ヘンゼルとグレーテル」:母親
- ポンキエッリ「ラ・ジョコンダ」:ラウラ
- R.シュトラウス「アラベラ」:アデライーデ
- R.シュトラウス「ナクソス島のアリアドネ」:作曲家
- R.シュトラウス「ばらの騎士」:オクタヴィアン
- R.シュトラウス「サロメ」:ヘロディアス
- ヴェルディ「ドン・カルロ」:エボリ
- ヴァーグナー「神々の黄昏」:ヴァルトラウテ
- ヴァーグナー「ローエングリン」:オルトルート
- ヴァーグナー「パルシファル」:クンドリー
- ヴァーグナー「ラインの黄金」:フリッカ
リリックアルト

では今度はアルトを紹介しましょう。アルトは女性の中でも最も音域が低いパートを担当しますが、それに伴い、声もより深みと丸みを帯びてきます。しかしアルトの声質を持った歌手というのは非常に少なく、またオペラにおいて大きな役柄というのもそれほど多くはありません。
ほとんどはメゾソプラノによって歌われる事が多いです。
大きな役柄は少ないと書きましたが、バロックオペラを入れるとまた話は変わります。バロックオペラではカストラート(声変わりする前に去勢された男性歌手)のために多くの大役が作曲されましたが、現代ではアルトやメゾソプラノ、もしくはカウンターテノール(裏声で歌う男性歌手)の歌手によって歌われる事が多いです。
それでは、ヘンデル「ジュリオ・チェザーレ」よりチェザーレが歌うアリア、 “Al lampo dellarmi“をアルト、ナタリー・シュトゥッツマンの演奏で聴いてみましょう。
チェザーレは当然男性の役ですが、音域はアルトの音域で書かれています。これは当時カストラートによって歌われたためです。現在は当然カストラートはいませんからメゾソプラノやアルトによって歌われる事が多いです。
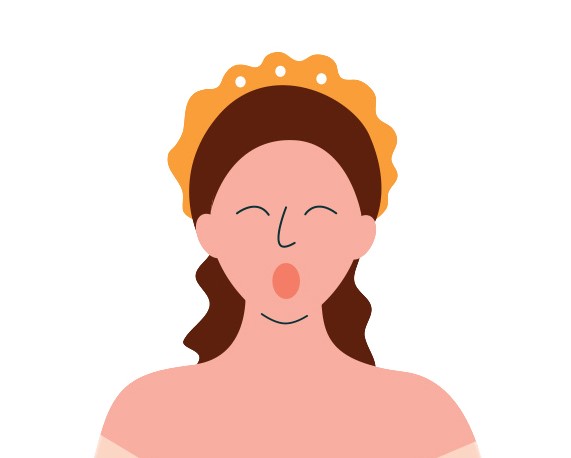
低いのに随分細かい音も沢山歌わなければいけないんですね。確かに最も低い音はちょっと男性っぽくも聞こえますわ。
アルトなので音域は低いですが、この時代のオーケストラは非常に小さいですから、声量もドラマチック性もそれほど必要とはしません。
- へンデル「アグリッピーナ」:アグリッピーナ
- ヘンデル「アルチーナ」:ブラデマンテ
- ヘンデル「ポロ」:エリッセナ/ガンダルテ
- ヘンデル「ラダミスト」:ゼノビア
- ロルツィング「ヴィルトシュッツ」:伯爵夫人
- モーツァルト「ミトリダーテ」:ファルナーチェ
- ロッシーニ「タンクレディ」:イザウラ
- プッチーニ「ジャンニ・スキッキ」:チエスカ
- ヴァーグナー「神々の黄昏」:フロースヒルデ
その他のアルト

さて、もうすぐこのコーナーも終わりが近づいてきました。いちおうキャラクター的に、アルトもブッフォアルトとドラマチックアルトに分類されます。ブッフォアルトはオペラにおいて喜劇的な役柄を担当します。ヴェルディの「ファルスタッフ」に登場するメグなどがその代表例です。
またドラマチックアルトとしては、マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」に登場するルチアがあげられますね。このオペラでは主人公の一人サントゥッツァがドラマチック・メゾソプラノによって歌われます。それに対してトゥリッドウの母親役であるルチアは、ドラマチックアルトとなっています。
若いサントゥッツァとの対比を声で表すために、年配のルチアはドラマチックアルトとより低い音域のソプラノが担当する事となっています。
「カヴァレリア・ルスティカ―ナ」の中には2重唱という程でもないですが、サントゥッツァとルチアが一緒に出てくる場面があります。メゾソプラノとアルトの場面はオペラの中でも非常に珍しいですね。アグネス・ヴァルツァ(サントゥッツァ)とヴェラ・バニエウィチ(ルチア)でお聞きください。
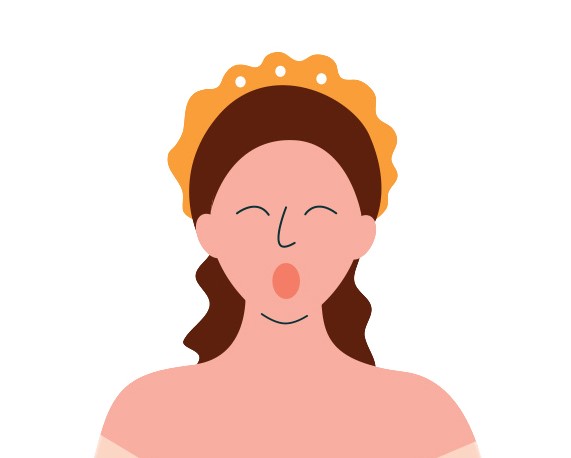
こうして聞き比べるとたしかに、ルチアの方が年をとった女性のように聞こえますわね。
- ヘンデル「アグリッピーナ」:ナルチスコ
- マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」:ローラ
- プッチーニ「外套」:フルゴラ
- リムスキー・コルサコフ「5月の夜」:ハンナ
- ヴェルディ「ファルスタッフ」:メグ
- マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」:ルチア
- ドボルジャーク「ルサルカ」:魔女
- ヘンデル「アリオダンテ」:ポリネッソ
- ヘンデル「ジュリオ・チェザーレ」:コルネリア
- ヒンデミット「サンクタ・スザンナ」:クレメンティーナ
おわりに
今回はメゾソプラノとアルトの声質の違いについて紹介しました。
繰り返しになりますが、この分野は現実的にはそこまで沢山歌手がいるわけではないので、だいたい劇場専属のメゾソプラノが全部を歌う事が多いです。私がいた劇場にはリリック・メゾソプラノが一人、そしてドラマチック・メゾソプラノが一人いましたが、これらの役柄を二人で分担して歌っていましたね。
さて、これで声種についての話も一通り終わりです。他の声種にも興味がある人はこれまでにも書いた記事がありますからぜひともご覧ください!
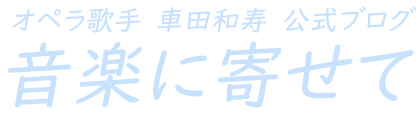


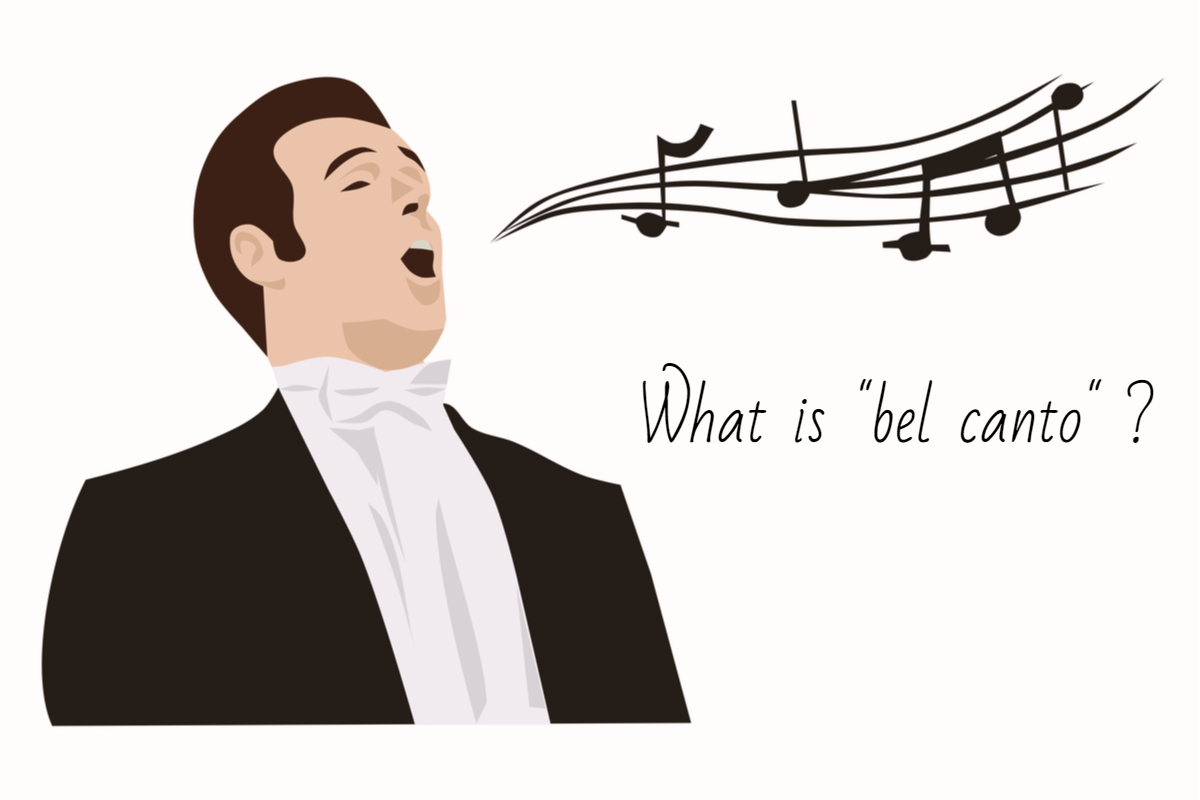















ソプラノと比べて確かに声の音色は違いますが、すごく細かい音を沢山歌わなければならないんですのね。